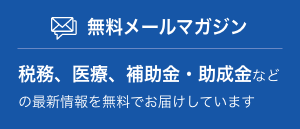中古物件のリフォーム費用で耐用年数が変わる?「簡便法」が使えなくなる50%ルールを解説
不動産投資や自社ビル取得の際、新築よりも利回りが高く、初期費用を抑えられる「中古物件」は魅力的な選択肢です。 しかし、購入に伴い大規模なリフォームやリノベーション(資本的支出)を行う場合、税務上の留意点があることをご存じでしょうか?
リフォーム費用があまりに高額になると、中古物件のメリットのひとつである「短い耐用年数(=購入初期に大きな減価償却費が計上)」が使えなくなる可能性があるのです。今回は、中古物件の耐用年数計算における「3つの区分」と留意点について解説します。
中古物件の「節税メリット」を決める耐用年数
通常、中古の建物を購入した場合、新築よりも短い「見積耐用年数」を使って減価償却を行うことができます。実務上は、以下の「簡便法」という計算式を使うのが一般的です。
- 法定耐用年数を全部経過している場合 → 法定耐用年数 × 20%
- 法定耐用年数の一部を経過している場合 → (法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
(※計算結果に1年未満の端数があるときは切り捨て、2年未満の場合は2年)
耐用年数が短くなれば、購入初期における単年度ごとの減価償却費(経費)が大きくなり、購入初年度から数年間の税金を抑える効果(キャッシュフローの改善)が期待できます。
リフォーム費用で変わる! 3つの計算ルール
しかし、購入に伴って建物の価値を高めるようなリフォーム(資本的支出)を行った場合、その金額によっては「簡便法」が使えなくなることがあります。 すなわち、税務上は、リフォーム金額の多寡に応じて以下の「3つの区分」に分けて処理する必要があります。
-
リフォーム費用が「建物購入価額の50%以下」の場合
判定:【簡便法】が使えます
リフォーム費用が、中古建物の購入価額(本体価格)の50%以下であれば、「簡便法」で計算した短い耐用年数を適用できます。 多くの小規模な修繕やリフォームはこの範囲に収まり、中古物件の節税メリットを享受できます。
-
リフォーム費用が「建物購入価額の50%超」かつ「再取得価額の50%以下」の場合
判定:【折衷法】が使えます
リフォーム費用が購入価額の半分を超えた場合で再取得価額の50%以下の場合には、単純な簡便法ではなく、建物本体(簡便法)とリフォーム部分(法定耐用年数)を、それぞれの金額比率で按分して平均する「折衷法(加重平均法)」という計算式を用います。なお、「再取得価額」とは「その中古物件と同じものを、今新築で買ったらいくらかかるか」という金額です。
<折衷法のイメージ> 耐用年数 = (建物本体価格 + リフォーム費用) ÷ (a + b)
- a = 建物本体価格 ÷ 簡便法の年数
- b = リフォーム費用 ÷ 法定耐用年数
簡便法よりは年数が伸びますが、新築扱いされるよりは短く済む、まさに「折衷」案です。
-
リフォーム費用が「再取得価額の50%超」の場合
判定:【法定耐用年数】が適用されます
リフォーム費用が「再取得価額」の50%を超えてしまうと、税務上は「実質的に新築同様になった」とみなされます。
この場合、簡便法や折衷法は使えず、新築と同じ「法定耐用年数」(例:事務所用である場合、鉄筋コンクリートであれば50年)を適用しなければなりません。 耐用年数が伸びるため、購入初期に大きな減価償却費が計上されるということはなくなり、想定していた節税効果が得られなくなる可能性があります。
まとめ:大規模リノベの前にシミュレーションを
「ボロボロの格安物件を買って、フルリノベーションでピカピカにして高収益を狙う」という投資手法は人気ですが、リフォーム費用が多額になると、税務上の耐用年数が「新築扱い」になってしまう可能性があります。
特に、「建物本体価格が安い」物件ほど、相対的にリフォーム費用の比率が高くなりやすいため注意が必要です。 大規模な修繕を計画されている方は、工事契約を結ぶ前に、税理士に依頼して耐用年数のシミュレーションを行うことをお勧めします。
当法人では、経験豊富な職員が税務・会計の専門知識をもって、貴社の成長を支援いたします。 サービスの概要や報酬についてのご相談は、まずはお気軽にお問い合わせください。