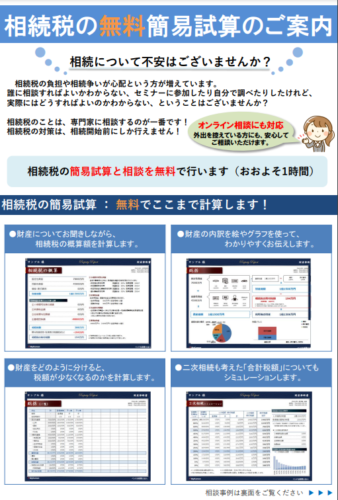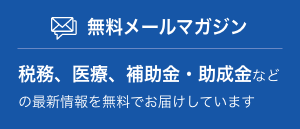相続時精算課税制度を介護に活用
遠方に住む老親の一人暮らしが難しくなり、介護施設の入所資金を捻出するため親の自宅を売却したい。これは、介護で直面しがちな状況です。
しかし、親が認知症になると売買契約を行うことが困難になります。
そこで、認知症になる前に子どもが自宅の贈与を受け、その後、介護施設に入所する段階になって子どもが自宅を売却して資金を確保することを検討しておくことも大切です。
認知症対策としての相続時精算課税贈与
親の自宅を子どもが贈与された場合、自宅の評価額に贈与税が課税されます。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
暦年課税の場合
まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、税率を乗じ贈与額を算出します。
親から自宅の贈与を受ける場合は「特例贈与財産」に該当するので、子どもに課される贈与税率は以下の通りです。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
特例贈与財産とは
| 直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により財産を取得すること ※受贈者が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること |
例えば自宅の評価額が3,000万円の場合、
- 基礎控除後の課税価格:3,000万円-110万円=2,890万円
- 贈与税額:2,890万円×45%-265万円=1,035万5千円
となります。
なお、贈与してから3年以内(2024年1月1日以後は7年以内※)に贈与者が亡くなった場合には、贈与財産は相続税の計算に含まれます。これを生前贈与加算といいます。
※移行期間があり、実質的に影響が出るのは2027年以後。加算期間が7年になる完全移行は2031年以後
相続時精算課税の場合
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を乗じた金額を算出します。
例えば自宅の評価額が3,000万円の場合、
- 特別控除後の課税価格:3,000万円-2,500万円=500万円
- 贈与税額:500万円×20%=100万円
となります。
2023年度の税制改正により、2024年1月からは相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。
この場合、
- 控除後の課税価格:3,000-110-2,500=390万円
- 贈与税額:390万円×20%=78万円
となります。
将来、相続が発生した時は、あらためて相続財産として加算され、先に納付した贈与税がある場合、受贈者の相続税額から控除して精算されます。
しかし、相続財産の価額が相続税の基礎控除額(3,000万円+相続人1人当たり600万円)の範囲に収まる場合には、相続税は課税されず、先に納付した贈与税の全部または一部が還付されます。
相続人が自分一人で他に資産がなく自宅の評価額が3,000万円の場合、相続財産が基礎控除内に留まるので、先に収めた78万円が還付されます。
親に自宅以外の大きな資産がなく、自宅評価額も基礎控除を超えないというこのケースでは、単純に贈与した場合の贈与税額が1,035万5千円にもなるのに比べ、相続時精算課税制度を利用すれば最終的な納税額はゼロになり、相続時精算課税制度が有効であることが分かります。
事前に贈与する場合の留意点
子どもが贈与を受けた親の自宅を売却した場合の譲渡所得の計算では、贈与者である親の取得時期と取得価額を引き継ぐため、その自宅の取得費を譲渡対価から控除できます。
しかし、子どもの居住用不動産でなければ譲渡所得の3,000万円特例控除※を受けることはできず、譲渡所得税の負担が大きくなるほか、翌年の国民健康保険料や介護保険料などが増加することにも留意が必要です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
| マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例 |
また、相続時精算課税を一度選択したら暦年課税に戻ることはできないので、基礎控除の110万円を超える贈与を毎年親から受けるたびに、相続時精算課税贈与としての申告が必要となります。
相続時に小規模宅地の特例の適用を受けることもできません。
小規模宅地の特例
| 相続などで一定の要件を満たす土地を取得した場合、一定の面積までの部分の評価額が最大80%減額される特例 |
ほかに、贈与のために名義変更をするにあたり、子どもに不動産取得税や登録免許税が発生すること、贈与後に親が引き続き住んでいても、固定資産税の納税義務者は子になることにも留意が必要です。
親に対する贈与課税はあるか?
一方、子どもが親の介護施設の入居一時金や施設利用料を負担した場合、子どもから親への贈与として課税されるのかが気になるところです。
この場合、扶養義務者間で生活に通常、必要な資金を贈与することは非課税とされますので、親に介護施設の入所資金などを負担する資力がなく、子どもが介護のために負担するのであれば非課税の扱いを受けることができるでしょう。
反対に介護に必要な水準を超え、老後生活を楽しむための豪華な施設の入所資金を負担するような場合は、子どもから親への贈与課税が生じる可能性がでてきますので注意を要します。
そして、何より大切なことは、親が長年慣れ親しんだ自宅を売却し、子どもに自身の生活を託すことへの信頼構築にあるのかもしれません。
相続・贈与についてお悩みの場合は、ペンデル税理士法人にぜひご相談ください。相続専門のスタッフが親身になってご相談にお答えします。
初回相談・お見積もりは無料です。詳しくは以下PDFファイルをご覧ください。